HOME
発表されたテーマ
 大空の会より
大空の会より 
子どもを亡くした家族に捧げるテーマⅣ
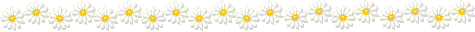
生と死のコンテンツ
『シルバー・バーチの霊訓』より
『シルバー・バーチの霊訓(七)』より
『シルバー・バーチの霊訓(六)』より
ナイチンゲール「愛の灯火」
『シルバー・バーチの霊訓(五)』より
『エジプトの死者の書』より
愛の原理
ユングの世界
『新樹の通信』について
『シルバー・バーチの霊訓(四)』より
大空の会より子どもを亡くした親たちに捧げるテーマⅢ
大空の会より子どもを亡くした親たちに捧げるテーマⅡ
大空の会より子どもを亡くした親たちに捧げるテーマⅠ
生と死のコンテンツ 
①子どもたちの手紙
『かみさまのてがみ』(サンリオ)という、子どもたちが神様に宛てた手紙を集めた本があります。エリック・マーシャルとスチュアート・ハンブルによって、子どもたちの手紙が集められましたが、アメリカ合衆国では128の新聞に連載され、NBCテレビの特別番組にもなって話題になりました。子どもたちの気持ちをより表すために、手書きの筆跡をそのまま生かし、綴りや文法の誤りも直さなかったこの本は、百万部以上も出版されました。その中から、神様へ宛てた子どもたちの手紙を、少しだけ取り上げてみましょう。
「あなたは、どうして じぶんが かみさまだって わかったんですか? シャーリーン」
「かみさま もし しんだあと いきるんなら、どうして にんげんは しななきゃいけないの? ロン」
「かみさま あなたは おかねもち? それとも ただ ゆうめいなだけ? スティーブン」
「かみさま どうして いちども テレビに でないの? キム」
②子どもたちの記憶その1
朝日新聞(2001年9月23日付)は、産婦人科医の調査結果から幼い子どもの53パーセントが胎内の記憶をもち、41パーセントが出生時の記憶をもっていると発表しました。
「NPO法人大空の会」のホームページの「発表されたテーマ」の『中間生を語る子ども』では、胎内の記憶、胎内に宿って行く時の記憶、天国での記憶、前世での記憶を持った子どもが登場します。
③子どもたちの記憶その2
ヴァージニア大学医学部教授、イアン・スティ-ブンソは、仲間の研究者と共に、世界中を長年かけて前世を記憶する子どもたちを追跡調査し、『前世を記憶する子どもたち』(日本教文社)を刊行しました。
彼らの注目すべき点は、文献を並べた卓上だけの研究ではなく、自分の足で世界各地に赴き、前世を記憶する子どもたちやその親たちと会って集めた2000件もの事例による研究発表というところです。前世を記憶する子どもたちの話を聞き、可能な場合には前世の家族と会い、死亡時の病院のカルテを取得します。また、前世の人物と生まれ変わった子どもとの対比や双方の家族の反応、更には何年か後にまた同じ子どもと会ってその様子を見るなど、徹底的に調査研究していきます。この長年にわたる世界各地での実績は、彼らの凄まじき行動力と探求心をうかがわせます。
②と③の子どもたちの記憶のように、生まれる前のことを語る子どもの話を、誰しも聞いたことがあるのではないでしょうか。幼い子どもたちは、私たちが少し前の出来事を話すように、生まれる前のことを話します。そこには、私たちが忘れてしまった生と死のコンテンツが含まれます。
私たちが生と呼んでいるものは、肉体をもち、物質の世界で生きることです。そして死と呼んでいるものは、生でないこと、つまりは肉体をもたないことです。
死とは無に帰すことと考える人もいますが、どのように捉えようと、それは自由です。しかし愛する人を亡くした時、どうしても心まで亡きものとなってしまったとは考えずらいようです。そして上記のような子どもたちの記憶に出会うと、この世に生まれる以前にも私たちの心は存在し、この世を去った後にも心は存在すると知らせてくれます。
①の子どもたちの手紙は、率直に神様に問いかけ、注文を付けて、神様が見たら驚くようなものばかりです。かわいく純真な手紙ですが、大人は鮮烈さを感じ、これまで気付かなかった見方と、新たな疑問に直面して、その解答を見つけるのも容易ではありません。
そして、特に私たちにとっては「かみさま もし しんだあと いきるんなら、どうして にんげんは しななきゃいけないの? ロン」という手紙は、衝撃的にさえ感じます。
亡き愛する人のために何かをしてあげたいという声をよく聞きます。けれど亡き愛する人に物質をプレゼントしても、彼らはそれを活用できるわけではありません。亡き愛する人にケーキをあげても、そのケーキを本当に食べるわけではなく、セーターをあげてもそれを身に付けるわけではありません。亡き愛する人と物質で交流するのではなく、純粋に心のみで交流することになります。
亡き愛する人が喜んでくれるものは、あなたが喜びをもっ生きてくれること、あなたが良き行ないを積んで生きてくれること、あなたの生が終わった時に、良き行ないを積んだ心をお土産に持ってきてくれることです。
亡き愛する人は、自分が逝ったせいであなたが嘆くことは望みません。美しい心となり、その美しい心を贈ってくれることを望みます。現実に私たちがこの世を生きていても、美しい心の人と出会うと喜びを覚えるように、亡き人の心も喜びを覚えます。
生きていくことは、様々な困難と出会うことでもあります。しかし死ぬということは、その人を亡くした私たちよりも環境の変化を伴います。だから、少しでも亡き人を応援できるよう、世の人々を助ける行動をし、美しい心を培いましょう。
「かみさま もし しんだあと いきるんなら、どうして にんげんは しななきゃいけないの?」とロンくんは聞きますが、それをより美しい心を培うために、人は何度も生と死を体験していくからだと思います。
瀬野彩子
参考文献
『かみさまのてがみ』エリック・マーシャル スチュアート・ハンブル(サンリオ)
『前世を記憶する子どもたち』イアン・スティーブンソン(日本教文社)
『シルバー・バーチの霊訓』より
1920年代後半から半世紀以上にわたり、古代霊シルバー・バーチが人々に霊言を訓示しました。それは英国の新聞王と言われたハンネン・スワッハー氏のホームサークルにおいて、モーリス・バーバネル氏を霊媒として行われ、世界に発信されていきました。そして、逡巡する人々の導きとなり、悩める人々の癒しとなって支えてくれています。
シルバー・バーチは、霊訓を地上にもたらした理由を以下のように語ります。
「私たちの霊団の仕事の一つは、地上へ霊的真理をもたらすことです。これは大変な使命です。霊界から見る地上は、無知の程度がひどすぎます。その無知が生み出す悪弊は、見るに耐えかねるものがあります。それが地上の悲劇に反映しておりますが、実はそれがひいては霊界の悲劇にも反映しているのです。
地上の宗教家は、死の関門をくぐった信者は魔法のように突如として言葉では尽くせないほどの喜悦に満ちた輝ける存在となって、一切の悩みと心配と不安から開放されるかに説いていますが、それは間違いです。真相とはよほど遠い話です。
死んで霊界に来た人は、初期の段階においては地上にいた時と少しも変わりません。肉体を棄てた、ただそれだけのことです。個性は少しも変わりません。性格はまったくいっしょです。習性、特性、性癖も個性も地上時代そのままです。利己的な人はあい変わらず利己的です。貪欲な人はあい変わらず貪欲です。無知な人はあい変わらず無知のままです。悩みを抱いていた人はあい変わらず悩んでいます。少なくとも霊的覚醒が起きるまではそうです。
こうしたことがあまりに多すぎることから、霊的実在についてある程度の知識を地上に普及させるべしとの決断が下されたのです。そこで私のような者が、永年にわたって霊的生命についての心理を説く仕事にたずさわってきたわけです。
霊的というと、これまではどこか神秘的な受けとられ方をされてきましたが、そういう曖昧なものでなしに、実在としての霊の真相を説くということです。そのためには何世紀にもわたって受け継がれてきた誤解、無知、偏見、虚偽、偽瞞、迷信、要するに人類を暗闇の中に閉じ込めてきた勢力のすべてと闘わねばなりませんでした。
私たちは、そうした囚われの状態に置かれ続けている人類に霊的開放をもたらすという目的をもって、一大軍団を組織しました。お伝えする真理はいたって簡単なものなのです。」
そして、シンプルに教えてくれます。
「神とは、法則なのです。あなたが正しいことをすれば、自動的にあなたは自然法則と調和するのです。」
しかし、そこには厳しさもあります。
「その法則が、構想においても働きにおいても完璧であるからには、当然その中に人間的な過ちに対する配慮も用意されているにきまっております。埋め合わせと懲罰が用意されております。邪悪の矯正があり、過ちと故意の悪行に対する罰があり、何の変哲もなく送った生活にもきちんとした裁きが為されております。」
それから、私達はどう生きていけばいいかを教えてくれています。
「特別に神から特権を授かる者は一人もいません。真摯なる者、謙虚なる者、ひたすらに真理を求める者、古い伝説や神話をかなぐり棄て、いったん受け入れた真理に素直に従う用意のできた者のみが、新しい世界の価値ある住民としての特権を得るのです。
教会といえども、法律といえども、裁判官といえども、インスピレーションの泉に蓋をすることはできません。その流れは止めどもなく続きます。みなさんは何者をも恐れることなく、人類を迷信の足枷から解き放し、無知の束縛から救い出す真理の擁護者としての決意をもって邁進しなくてはいけません」
また、シルバー・バーチの以下の言葉は、私達を必死で救おうとしていることが窺いとれます。
「私たちの勢力は、生命が永遠であること、人類は例外なく死後も生き続けること、愛に死はなく、死者への哀悼は無用であること、そして宇宙には誰でも分け隔てなく与えられる無限の霊的叡智と愛とインスピレーションの泉があることを教えたくて戻ってくる男女によって編成されているのです。」
一時の地上の隆盛や俗念に左右されることなく、普遍の真理を貫ける美しい今世を私達に生きて欲しい、シルバー・バーチも天界の子ども達も、そう望んでくれているのでしょう。
瀬野彩子
参考文献
『シルバー・バーチの霊訓』 潮文社
『古代霊は語る』 潮文社
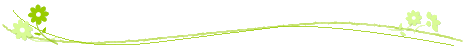
『シルバー・バーチの霊訓(七)』より
シルバー・バーチの霊訓は、1920年代後半から50年余りにわたり、モーリス・バーバネル氏という霊媒を通じて語られました。シルバー・バーチによると、それは天界の一霊団により構成されています。その中には、かつて地上に生きた人もいて、複数の男性のインディアンと英国人、二人の英国女性、二人の国教会の牧師、一人の著名なジャーナリスト、一人のアラブ人、一人のドイツの化学者、一人の中国人も含まれます。霊団は、人種、年代を超えて構成され、あらゆる角度より、シルバー・バーチの霊訓をサポートしているようです。そして、英国の新聞王と言われたハンネン・スワハーのホームサークルで、いつものメンバーと数人の招待客の前で行なわれました。
ある日のこと、息子の死に心を痛めていた夫婦が招待されました。シルバー・バーチは、彼らにこのように言いました。
「あなたが嘆き悲しむ時、それは実はわが子を失った自分の身の上を悲しんでいらっしゃるのであり、(肉体的に)自由の身となった息子さんのことを悲しんでおられるのではありません。あなたは、見慣れたあの姿が見られなくなったことを淋しがっておられるのです。物体自体が二度と見られなくなったことを、嘆いておられるのです。
しかし、本当の息子さんは立派に元気で生きておられるのです。ただその手で触ってみることができないだけです。
どうかその物的感覚の世界、五感というお粗末な魂の窓の向こうに目をやり、霊的実在を知ることによって得られる叡智を、身につけるように努力なさってください。」
しかしシルバー・バーチは、わが子を亡くした大変さを分かっていないわけではありません。
「真理を魂の中核として受け入れる備えができるまでには、あなたはそのために用意される数々の人生経験を絶え忍ばなくてはなりません。その時点においては辛く苦しく無情に思え、自分一人この世から忘れ去られ、無視され、一人ぼっちにされた侘びしさを味わい、運命の過酷さに打ちひしがれる思いをされたことでしょう。」
それら喪失の大変さを、どのように対処していけばいいのでしょうか。シルバー・バーチは、何らかの助力をしてくれるのでしょうか。
「私が、その摂理を変えるわけにはいかないのです。私は、ただ摂理はこうなっていますよとお教えするだけです。これまで私は何度か皆さんが困った事態に陥っているのを見て、その運命を何とか肩代わりしてあげたい、降りかかる人生の雪と雨と寒さから守ってあげたいと思ったことがあります。しかし、それは許されないことなのです。なぜなら、そうした人生の酷しい体験をさせている同じ力が、人生に光と温もりをもたらしてくれるからです。一方なくして他方は存在しないのです。試練と体験を通じてこそ霊は成長するのです。」
どうして成長しなければいけないのでしょうか。
「それぞれの界に住む霊の成長には大きな差があるのです。こちらでは魂の成長に応じた界、つまりその人の知性と道徳性と霊性の程度にちょうどよく調和する界に住むようになります。界の違いはそこに住む人の魂の程度の違いだけで、霊性が高ければ高いほど、善性が強ければ強いほど、親切心が多ければ多いほど、慈愛が深ければ深いほど、利己心が少なければ少ないほど、それだけ高いレベルの界に住むことになります。
地上はその点が違います。物質界という同じレベルで生活しているからといって、みんな精神的に、あるいは霊的に、同じレベルの人たちばかりとは限りません。身体は同じレベルのもので出来ていますが、その身体つまり物質でできた肉体が無くなれば、魂のレベルに似合ったレベルの界へ行くことになります。」
先立った愛する人のことを考えた時、その霊的レベルの高さを思わずにいられないことは、よくあります。先立った愛する人に、少しでも近付くことを望むならば、あなたの霊的レベルを高めることです。
「奉仕こそ魂の通貨なのです。いつどこにいても、人のために自分を役立てることです。神学などはどうでもよろしい。教義、儀式、祭礼、教典などは関係ありません。祭壇に何の意味がありましょう。尖塔に何の意味がありましょう。ステンドグラスの窓にしたからといってどうなるというのでしょう。法衣をまとったからといってどう違うというのでしょう。そうしたものに惑わされてはいけません。何の意味もないのです。
人のために自分を役立てることです。あなたの住むその世界のために役立てるのです。人の心を思いやり、やさしくいたわり、気持ちを察してあげなさい。」
何故、愛する人の死という極限の思いを、今世において体験したのか。それはより人の心を思え、奉仕の活動こそ喜びであることに、気付くためだったのでしょう。今、地上にいる私達は、愛する人の死を無駄にしないためにも、日々より良き心で、日々どんなことにも奉仕の精神で、日々より美しい魂となるよう、生きていくことが望ましいとシルバー・バーチは教えてくれます。
瀬野彩子
参考文献
『シルバー・バーチの霊訓(七)』 潮文社
『古代霊は語る』 潮文社
 『シルバー・バーチの霊訓(六)』より
『シルバー・バーチの霊訓(六)』より
古代霊シルバー・バーチは、1920年代より50年にわたり、イギリスのハンネンスワッハー氏のホームサークルにおいてモーリス・バーバネル氏を霊媒とし、古代霊シルバー・バーチが人々に霊言を訓示しました。その霊言は世界に発信されましたが、今も世界中の人々の生きていく指箴となり、重宝されています。
「最高の成果を得るためには顕幽両界の間にお互いに引き合うものがなければなりません。その最高のものが、愛の力なのです。両界の間の障害が取り除かれていきつつある理由は、その愛と愛との呼びかけ合いがあるからです。」
と、シルバー・バーチは言います。するとホームサークルのメンバーが、
「霊界の仕事が金銭的になりすぎるとうまく行かないのは、そのためでしょうか。」
と、シルバー・バーチに質問しました。
「その通りです。霊媒はやむにやまれぬ献身的精神に燃えなければなりません。その願望そのものが霊格を高めていくのです。それが何よりも大切です。なぜなら、人類が絶え間なく霊性を高めて行かなかったら、結果は恐ろしいことになるからです。霊がメッセージをたずさえて地上へ戻ってくるそもそもの目的は人間の霊性を鼓舞するためであり、潜在する霊的才能を開発して霊的存在としての目的を成就させるためです。」
と、シルバー・バーチは答えました。
また二人の息子を大戦で失った夫婦に、シルバー・バーチは次のような言葉を述べました。
「霊の力に導かれた生活を送り、今こうして磁気的な通路(霊媒)によって私どもの世界とのつながりをもち、自分は常に愛によって包まれているのだという確信を持って人生を歩むことができる方をお招きすることは、私どもにとって大いに喜ばしいことです。お二人は神の恵みをふんだんに受けておられます。悲しみの中から叡智を見出されました。眠りのあとに大いなる覚醒を得られました。犠牲の炎によって鍛えられ清められて、今お二人の魂が本当の自我に目覚めておられます。・・・
お二人は悲痛の淵まで降りられました。魂が謀反さえ起こしかねない酷しい現実の中で、人間として最大の悲しみと苦しみを味わわれました。しかし、その悲痛の淵まで降りられたからこそ喜びの絶頂まで登ることもできるのです。・・・
なぜなら人生とは絶え間ない闘争であり、障害の一つ一つを克服していく中に、個性が伸び魂が進化するものだからです。いかなる困難も、いかなる苦痛も、いかなる難問も、あなた方を包んでいる愛の力によって駆逐できないものはありません。それはみな影であり、それ以上のものでもそれ以下のものでもありません。訪れては去っていく影にすぎません。・・・
そうした営みの中で、お二人は悲しみというものが仮面をかぶった霊的喜悦の使者であることを悟るという計画があったのです。悲しみは、仮面です。本当の中身は、喜びです。仮面を外せば、喜びが姿を見せます。・・・
地上的な財産にしがみつき、霊的な宝をないがしろにする者は、いずれ、この世的財産は色あせ錆つくものであることを思い知らされます。霊的成長による喜びこそ永遠に持続するものです。」
そしてシルバー・バーチは、以下の言葉で私達を励ましてくれました。
「魂を本来の豊かさの存在する高所まで舞い上がらせてください。そこにおいて本来の温もりと美しさと光沢を発揮されることでしょう。」
瀬野彩子
参考文献
『シルバー・バーチの霊訓(六)』 潮文社
『古代霊は語る』 潮文社
 ナイチンゲール「愛の灯火」
ナイチンゲール「愛の灯火」
看護の祖として知られるフローレンス・ナイチンゲールは、1820年に両親の旅行先であるイタリアのフィレンツェで生まれました(フローレンスは、フィレンツェの英語名)。
ナイチンゲールが生まれた家は、財産家で何不自由ない暮らしでしたので、人から見れば幸せと映りました。しかし、ナイチンゲールは6歳の頃より、「私は幸せでない」と思い始めていました。後に自分の時間も労力もつぎこんで看護に生き甲斐を見い出していく人でしたから、人も羨む財産は、彼女にとって何の魅力もなかったのでしょう。
1837年2月7日、ナイチンゲールの日記には、神の声を聞いたと記されています。ナイチンゲールの寝室に茨の冠をかぶったキリストが光り輝く姿で現れ、「我に仕えよ!」と伝えたそうです。彼女は、その声をはっきり聞いたと言っています。そしてナイチンゲールは看護師になりたいと望み、それを実現していきます。
ナイチンゲールのその体験より思い起こすのは、マザーテレサです(参照:第53回大空の会のテーマ「マザーテレサその愛」)。1946年9月10日に、マザーテレサはインドのダージリン行きの汽車に乗っていました。そこで、「すべてを捧げてスラム街にまであのお方、キリストに従い、貧しい人の中で、その方に仕えよ。」と、はっきりと神の声を聞いたと言っています。それからマザーテレサは、その神の言葉に従い、貧しい人達を助け、その活動を世界へ普及させていきました。
ナイチンゲールもマザーテレサも、神の声をはっきり聞いたと言い、それを実行した人生をおくりました。神の声を聞ける御二人は、その神の指示に、我が身を霊媒として捧げたのではないでしょうか。御二人のされたことは、安楽的な理想や憧憬により出来る行為ではなく、ましてやそれを活き活きと行いました。それは、この世の人の決める幸・不幸を採寸する定規を所持しない、天からの導きを得る喜びがあったからではないでしょうか。 故に、御二人とも常に過酷な反撃を受けていながらも、生涯を通じて心楽しく行えたのではないではないかと思います。
ナイチンゲールの名を一躍有名にしたものは、1854年より勃発したクリミア戦争でした。ナイチンゲールは看護団を率いて、傷病兵達を看護するために戦地の病院に入りました。しかしそこは、血と泥で汚れ、鼠が走り回り、傷病兵の身体は蛆がわき、薬品も包帯も不足しているという悲惨さでした。また食料も酷いものでしたが、彼らに与えられる一日の水の量さえ足りないという状態でした。
ナイチンゲールは看護団を指示しながら、掃除、洗濯、看護と忙しく立ち働きます。しかし軍医長のホール博士は、目まぐるしく病院を改善していくナイチンゲールを好ましく思わず、反感をもって辛辣に当たっていきます。そんな中でもナイチンゲールは、自分の考える看護を実践していきました。
そして昼ばかりでなく夜にも、ナイチンゲールはランプを持って、傷病兵達の様子を見て回っていきました。そのことから彼女は、「ランプの貴婦人」と呼ばれています。ナイチンゲールがいてくれることによって、どれほどに傷病兵達は癒されたことでしょう。ナイチンゲールの絶え間ない努力により、病院内の死亡率は42パーセントから5パーセントへと下がります。
このことはイギリス本国にも伝えられ、ナイチンゲール人気が沸騰します。が、ナイチンンゲールはクリミア病(チフス)に罹り、倒れます。本国では多くの人がナイチンゲールの快復を祈ったと言われます。それからナイチンゲールは奇跡的に快復したかに見えました。本復ではなかったのですけど、ナイチンゲールはまた活動的に働き出します。
1856年にクリミア戦争は終結、病院に残った最後の傷病兵を見送ってから、ナイチンゲールは帰国します。本国ではナイチンゲールを熱狂的に迎え、ヴィクトリア女王はアルバート公(ヴィクトリア女王の夫)がナイチンゲールのためにデザインしたブローチを贈り、その勲功を讃えました。
しかしナイチンゲールの身体は、クリミア戦争での激務がたたり、それから1910年に90歳で死亡するまで、あまり外に出られなくなりました。でもその分、ナイチンゲールは自身の中にある著述の能力を活かしていきます。
まずは、陸軍大臣のシドニー・ハーバートと陸軍の改革を推し進めていきます。陸軍の会議にナイチンゲールの出席は叶いませんでしたが、読み上げられる文書は彼女が書いたものでした。またハーバートによりナイチンゲール基金が創設され、多くの貧しい兵士達も寄附を寄せました。そして、ナイチンゲール看護師訓練学校も開設されます。
しかしその改革の途中で、ハーバートは亡くなります。彼の最期の言葉は、「かわいそうなフローレンス・・・。かわいそうなフローレンス・・・。私達の共同の仕事・・・、まだ終わっていない・・・、やっている最中・・・。」だったと言われます。ハーバートが他界すれば、それをナイチンゲールと共に行う陸軍の上層部の者はおらず、むしろ大っぴらに批判されて中断されることを、彼は憂いていたのです。
ナイチンゲールは、陸軍の改革には手を引かざるを得なかったものの、看護とはどういうものかを事細かく書き記し、世の中に訴えていきます。特に『看護覚え書』という著書は、今も多くの人に活用されています。また、衛生状態と死亡率や失病率などの関係を統計して世に広め、病院建築の設計も行い、当時イギリスの植民地であったインドの衛生改善も指導しました。
それからナイチンゲール看護師訓練学校では、彼女の方針に添った看護師を養成していきます。学生一人一人をチェックし(そのチェックの紙は今も遺っています)、怠け癖のある者や看護師に向かないと思う者は、すぐに退学させていきました。そして優秀な看護師をつくり、イギリス国内だけでなく世界へと、病院改革のために派遣されていきました。
ナイチンゲールのおかげで、世の中の衛生や看護が見直されました。しかし、そこにはナイチンゲールが生きている間に辿った多くの苦労が含まれています。ナイチンゲールに感謝しつつ、生を歩めていけたらと思います。
瀬野彩子
参考文献
『看護覚え書 ―看護であること 看護でないこと―』フローレンス・ナイチンゲール(現代社)
『看護覚え書 普及版』フローレンス・ナイチンゲール(うぶすな書院)
『ナイチンゲール 心に効く言葉』フローレンス・ナイチンゲール(サンマーク出版)
『ナイチンゲール言葉集』フローレンス・ナイチンゲール(現代社)
『ナイチンゲール伝』リットン・ストレイチー(岩波文庫)
『世界の伝記 ナイチンゲール』足沢良子(ぎょうせい)
『ナイチンゲール 神話と真実』ヒュー・モール(みすず書房)
『シルバーバーチの霊訓(五)』より
「みなさんは他界した人が、ぜひ告げたいことがあって、地上に戻ってきても、有縁の人たちが何の反応も示してくれない時の無念の情を、想像してみられたことがあるでしょうか。大勢の人が地上を去ってこちらへ来て、意識の焦点が一変し、はじめて人生を正しい視野で見つめるようになり、何とかして有縁の人々に嬉しい便りを伝えたいと思う。その切々たる気持を察したことがおありでしょうか。
ところが人間が一向に反応を示してくれません。聞く耳をもたず、見る目ももちません。愚かにも人間の大半は、この粗末な五感が存在のすべてであり、それ以外には、何も存在しないと思い込んでおります。
私たちは、大勢の霊が地上へ戻ってくるのを見ております。彼らは何とかして、自分が死後もいきていることを知らせたいと思い、あとに残した人々に両手を差し伸べて近付こうとします。やがてその顔が、無念さのこもった驚きの表情に変わります。もはや地上世界に何の影響も行使できないことを知って、愕然とします。どうあがいても、聞いてもらえず、見てもらえず、感じてもらえないことを知るのです。情愛にあふれた家庭においてもそうなのです。」
と、古代霊シルバー・バーチは、言います。
また、
「霊視に、高額のお金を取っている霊能者と称す者は、偽者と言えましょう。たとえ霊が見えても、低級霊しか見えないのです。そういう所へ行くと、依頼者の心身は一時的には良くなったような気がしても、実際は坂道を転がるように、奈落へと突き落とされ、ますますそういう者に取りすがられ、抜けられなって行くことが多いようです。もし気が付けば、多額の金銭を取られているばかりでなく、心に傷を植付けられていることが分ります。しかし本当は、そればかりではありません。有縁の霊も悲しみ、傷つけているのです。それが見えれば、あなたの心は、どれほどに悔い、どれほどに嘆き悲しむでしょうか。
事は簡単です。たとえ優しく接されようと、霊視に金銭売買する者からは逃げることです。たとえ表面を飾ろうとも、そういう者の霊格は低く、心はどろどろと汚れているのですから。」
と記されています。
「ご承知のように私は常に一人でも多くの(本物の)霊媒が排出することの必要性を強調しております。霊界からの知識、教訓、愛、慰め、導きが地上に届けられるためには、ぜひとも霊媒が必要なのです。一人の霊媒の輩出は、物質万能思考を葬る棺に打ち込まれるクギの一本を意味します。神とその霊的真理の勝利を意味するのいです。霊媒の存在が、重要である理由は、そこにあります。両界をつなぐ媒体だからです。」
と、シルバー・バーチは教えてくれます。
「モーゼスの『霊訓』によると、かの"十戒"を授かったモーゼが従えていた七十人の長老は、みな霊性の高い人物だったという。これは、世界に共通した事実であって、古代においては、霊感が鋭くかつ霊的なことに理解のある者が要職につき、いわゆる祭政一致が当然のこととされた。
それが物質科学の発達とともに意識の焦点が、五感へと移行し、物的な物差しで測れないものが否定されていった。ところが皮肉なことに、その物質の本質は常識的に受け止めてきたものとは違って、ただのバイブレーションにすぎないことを突きとめたのと時を同じくして、再び霊的なものへの関心が高まりつつある。
シルバー・バーチは、そうした潮流の背後には、霊界からの地球的規模の働きかけがあることを指摘している。オーエンの『ベールの彼方の生活』第四巻"天界の大群"編は、それを具体的に叙述している。」
と『シルバー・バーチの霊訓(五)』に書かれています。
「人間の歴史において大きな革命を生んできたのはすべて霊の力です。今その霊力が、かつてと同じ"しるしと奇跡"を伴って再び顕現しております。・・・肉親を失った人たちに慰めをもたらしております。
肉眼の視野から消えると、あなた方は、悲しみの涙を流されますが、私たちの世界ではまた一人物質の束縛から解放されて、言葉で言い表せない生命のよろこびを味わいはじめる魂を迎えて、うれし涙を流します。私はいつも"死"は自由をもたらすものであること、人間の世界では哀惜の意を表していても、本人は新しい自由、新しい喜び、そして地上で発揮せずに終った内部の霊性を発揮する機会に満ちた世界での生活を始めたことを知って喜んでいることを説いております。
ここにおいでの方々は、他界した者が決してこの宇宙からいなくなったのではないとの知識を獲得された幸せな方たちですが、それに加えてもう一つ知って頂きたいのは、こちらに来て霊力が強化されると、必ず地上のことを思いやり、こうして真理普及のために奮戦している吾々を援助してくれているということです。」
とシルバー・バーチは、有縁の霊があなたに向けている愛を、教えてくれます。
瀬野彩子
参考文献
『シルバー・バーチの霊訓(一)~(十二)』 潮文社
『ベールの彼方の生活』 オーエン・G・V 潮文社

『エジプトの死者の書』より
世界最古の死者の書である『エジプトの死者の書』は、エジプトのヘセプーチ王の治世である紀元前4300年頃に発見されました。その多くは、墓石や石棺や石碑に絵文字で描かれていました。そして、それは6000年以上を経た今でも伝承され続け、出版され、読み継がれ、語り継がれています。
エジプトの人達は、死後に人は「バー」という鳥の姿になって、肉体からあの世に飛び立つと考えていました。だから、鳥の形に似た絵文字で霊魂を表しています。
シカゴ大学医学部教授だったエリザベス・キューブラー・ ロス博士(1926年~2004年)は、ナチスの強制収容所で殺された子ども達や不治の病などで死へと向かった多くの子ども達は、死の前に自分の姿を蝶の姿にして絵で表したと著しています。(参照:第23回大空の会のテーマ「幼い子どもが教える天国への旅立ち」)
また第27回大空の会のテーマの「中間世を語る子ども」では、四歳の子どもが生まれ来る前は、飛んでいたと話しています。どのように飛んでいたかと訊くと、「ウルトラマンのように飛んでいた」と答えました。
このように太古より近年、現代に至るまで、霊魂というものは飛ぶということが、あらゆる場面で顕されています。
『エジプトの死者の書』では、アニという名前の男性が登場します。彼の生前は、王宮の書記官でした(アニが生きていたのは、紀元前4500年頃とされ、歴史的にも確認されています)。アニは、彼が言うところの「人体出現の技術」を使って、当時の霊媒の前に現れ、交流しました。そこには霊が語る赤裸々な話があります。
「霊界のことをさまざまに語りたい、これが私の気持ちだ。霊界のことを多く知っているが、それはあくまで今の私のことだ。霊界に入った頃の私は、まさに霊の幼児で、何も知らず、何もわからず、ただぼんやりしていたり、面食らってばかりいた。その頃の気持ちは、たとえて言うならば、母の胎内から初めて人間界に生を享け、産声を上げたばかりの赤子と同じだった。 ・・・
ある朝、いやこの世と同じように朝という言葉でいうのが正しいかどうかは知らない。しかし、私自身にはそれは朝と感じられた。そのある朝、私は自分が眠っているとも、目覚めているともはっきりしない状態の中で、傍らに人がいるのを感じた。その人は『あなた、あなた・・・』と呼びながら、私のひじをつついているような気がした。私は目を開けて見た。すると、そこに妻が立っていたのである。『ああ、お前か、もう朝か?』私は声に出して、そう妻に問いかけようとして、その声を飲み込んでしまった。私の妻は、私より前に死んでいたのである。死んだ妻がいるなんて、おかしい。そんなことは有り得ないではないか。
私は、妻を愛していた。だから、夢に妻が現れてもおかしくはない。『なんだ、夢か』私は再び眠りに落ちようとした。そして、その前にもう一度目を開けて見た。夢ならば消えて
いるはずの妻の姿は、前よりもいっそうはっきりした姿となって、そこにいた。
それに、かすかな笑みさえ浮かべているのだ。否々、それだけではない。亡き妻は口を開いて言ったのである。『やっと気が付いたのね、よかったわ!』
この時の私の驚きは、如何ばかりであろう。それは、話しても信じてもらえないほどの驚きであった。驚きをしずめてくれるためだったに違いない、妻は優しくにこやかな笑顔になっていた。『あなた、あなたは1度死んで、いま新しく生まれたのよ』
私は、こうして愛する亡き妻に逢えたのである。妻は、人間としての私は死んだこと、今いるのが人間の世界とは別の世界の霊界であることなどを、霊界の赤子の私に教えてくれた」
人間が、この世から霊界というところへ戻った時(つまりは死した時)のことについては、コナン・ドイル(1859年~1930年)も語っています。コナン・ドイルは、シャーロック・ホームズの著者ですが、その生涯のほとんどを霊性普及に捧げました。彼が亡くなった後に、霊媒のミネスタという女性を介し、メッセージが人々に送られました。(参照:第33回大空の会のテーマ「コナン・ドイルのメッセージ」)コナン・ドイルも、霊界に戻って来た時の、大変な様子を伝えてくれています。
また、日本でも昔から人が亡くなった時には「お迎えが来る」という言葉があります。それに、世界中の死期が迫った人々がお迎えの人を見ているという報告が多数あり、「デスベッド・ヴィジョン」とも呼ばれています。(参照:第30回大空の会のテーマ「お迎えの人々」)
エジプトの死者の書においても、アニが亡くなった時、最愛の妻、ツツが迎えに来てくれて、再会を果たしました。そしてツツは、アニの霊界への導きの役を行ってくれています。
「この体験を通して私が知り得たのは、我々は決して死んだり、亡びたりはしない。1度だって、死んだりしないということだ」と、アニは語っています。
エジプトの死者の書では、葬儀の行い方や経文の上げ方なども取り上げられていますが、死後に死者はどうなっていくかを書いたものが多くあります。人は死しても生前を記憶すると解釈し、あるいは死した人に伝え、死への道案内の助けとしたようです。だからこそ墓石や石棺などに書かれているものが多いのでしょう。
太古より伝わる死者の書と呼ばれる書物は数ありますが、どれも死など存在しない魂の永遠を謳って止みません。
瀬野彩子
参考文献
『世界最古の原典 エジプト死者の書』ウオリス・バッジ(たま出版)
『エジプトの死者の書』石上玄一郎(第三文明社)
『図解エジプトの死者の書』村治笙子 片木尚美 仁田三夫(河出書房新社)
 愛の原理
愛の原理
「人間はなぜ戦争をするのか。・・・なぜ悲劇を繰り返すのか、その原因は何だと思いますか。なぜ人間世界に悲しみが絶えないのでしょうか。」
と、古代霊シルバー・バーチは問います。
この場合の戦争とは、国同士の大きな戦争もそうですが、個人間での諍いも含まれるように思います。ニュースでは、毎日のようにその日に起きた悲劇が報道されています。しかし公表されるものだけでなく、悲劇は各所にあります。
「人間は何かにつけて、差別をつけようとします。そこから混乱が生じ、不幸がうまれ、そして破壊へと向かうのです。」
と、シルバー・バーチは言います。
「あなたがた文明人は、物質界にしか通用しない組織の上に人生を築こうと努力してきました。言いかえれば、本来の摂理から遠くはずれた文明を築かんがために教育し、修養し、努力してきたということです。人間世界が堕落してしまったのはそのためなのです。・・・人間が物質によって霊眼が曇らされ、五感という限られた感覚でしか物事を見ることが出来ないために、万物の背後に絶対的統一原理である宇宙の摂理が宿っていることを理解できないからです。・・・大事なものはただひとつ、愛だということです。それ以外のすべて、学業とか、学位とか、財産とか、ミンクのコートを何着もっているかなどといったことは、どうでもいいのです。
ただひとつ重要なことは、やるべきことを如何にやるかです。そして大事なことは、愛をもってそれをやるということです。・・・古い時代の文明が破壊したように、現代の物質文明は完全に破壊状態に陥っています。その瓦礫を一つ一つ拾い上げて、束の間の繁栄でなく、永遠の摂理の上に今一度文明を築き直さなければなりません。そのお手伝いをするために私どもは地上に戻ってまいりました。それは、私どもスピリットと同様に、物質に包まれた人間にも、神の愛という同じ血が流れているからに外なりません。・・・何とおっしゃろうと、霊界と地上とは互いにもたれ合って進歩して行くものなのです。」
と、シルバー・バーチは教えてくれます。
また、コナン・ドイルは次のように説きます。
「自らを傷つけることなく他人を傷つけることは不可能であると知るでしょう。人を憎み、戦うべく戦争に行くというのは自分自身との戦いに赴くことにほかならないのですから。・・・同胞愛以外の生き方などというものは、世界が歩むべき道の選択肢として開かれてはいないのです。・・・すべての命、自分自身の命も他のすべての人々の命も、一つの巨大な愛の心のなかに存在するのだということを、そして自分の肉体としての生命は、その巨大な愛の心で息づいているのだと悟らなければなりなりません。
そしてマザー・テレサは、こう言います。
「人間にとって最も大切なのは、人間としての尊厳を持つことです。パンがなくて飢えるより、心や愛の飢えのほうが重病です。豊かな日本にも貧しい人はいると思いますが、それに気付いていない人もいるでしょう。」
人間の尊厳とは、何なのでしょう。インドでは多くの人々が路上で生まれ、路上で暮らし、路上で死んでいきます。マザー・テレサは、こういう人達が死に行く時、彼らを引き取ります。クリスチャンであるマザー・テレサは、彼らのことをキリストであるとし、心を込めて介護し、死へと見送ります。
マザー・テレサのもとには、多くのシスター達がいて、今もマザー・テレサの志しを受け継いでいます。シスター達は、裕福な家の子女が多いそうですが、多くの物品に囲まれたかつての生活よりも、サリー二枚とその洗濯用のバケツだけしか持たず、毎日奉仕の生活である今の方がはるかに楽しいと言います。彼女達の心は、人間愛という豊かさに恵まれたゆえ、本当の楽しさを知り、物質に左右されないという魂としての尊厳を得られたのだと思います。
「人生は愛すること。そして愛されることの喜びそのものです。愛は与えることで一番良く表現されうるのです。そして、いま学びにあるあなた方は、この与えることが痛むまで与えることを学ぶのです。何故ならば、これこそが本当の愛の証だからです。」
という言葉を、マザー・テレサは遺しています。
「生活態度が立派であれば、それだけ神の道具として立派ということです。ということは、生活態度が高度であればあるほど、内部に宿された神性がより多く発揮されていることになるのです。」
と、シルバー・バーチが教示し、
「周波数の高いレベルに思考を合わせれば、調和の取れた豊かな実りが約束されるでしょう。」
と、ジェームズ・ヴァン・プラグが講じます。
最後に、シルバー・バーチのこの言葉を援用します。
「あなたが片時も一人ぼっちでいることはないことはご存知でしょう。人のために尽くそうとされるその願望は自動的に私どもの世界で同じ願望を抱く博愛心に燃える霊を惹き寄せます。なぜならば双方に理解力における親和性があるからです。・・・私どもは肩書きも党派も教義も宗教も興味ありません。その人がその日常生活において何を為しているかにしか興味はないのです。・・・永遠に変わらぬものは愛です。人のために尽くしたいという願望から発する真実の愛です。・・・愛こそがあなたの悟りを開く大きな助けとなります。」
瀬野彩子
参考文献
『シルバー・バーチの霊訓』(潮文社)
『コナン・ドイル 人類へのスーパーメッセージ』アイヴァン・クック(講談社)
マザー・テレサ初来日(1981年4月)の語録
『マザーテレサ あふれる愛』沖守弘(講談社)
上智社会福祉専門学校・創立25周年記念誌へのマザー・テレサのメッセージ
『天国との会話』ジェームズ・ヴァン・プラグ(光文社)
 ユングの世界
ユングの世界
夢分析で知られるカール・グスタフ・ユングは、1875年にスイスのボーデン湖畔、ケスヴィルの牧師の家に生まれました。ユングの父方の祖父は、ゲーテの私生児だったそうですが、ユングはそのことに対して、ある意味誇りをもった発言を多くのこしています。ユングの母方のプライスヴェルク家は、霊能者の家系であり、親戚の者が入神した様子を、ユングは自分の書物に記しています。ユングはバーゼル大学に学び、1902年にチューリッヒ大学で博士号を取得、翌年にエンマ・ラウシェンバッハと結婚します。
運命の出会いとも言えるジークムント・フロイトとは、1906年より文通をはじめます。フロイトとユングは、師匠と弟子という関係でしたが、お互いを訪ね合ったり、共に渡米したりと蜜月のような年月を過ごします。しかし、夢という同じ題材を研究する二人でしたが、捉え方に根元的な違いがありました。霊的なものを信じないフロイトは夢を解く鍵を、肉体が持つ欲求とその心理にあると主張し、ユングは夢とは見た人の今世ばかりに起因するのでなく、外的な啓示も含むとしました。芸術家ゲーテの血を引き、霊能者の家系であるユングにとって、夢の霊性を唱えることは、至極当然のことだったのでしょう。
1909年、フロイト邸でフロイトとユングが予知夢や超心理学について語り合っていました。もちろん合理主義者のフロイトは、そんなものを肯定する筈がありませんでした。ユングは、その時に起こった出来事を次のように自伝に書いています。
「フロイトがしゃべっている間、私は奇妙な感覚を感じた。まるで横隔膜が鉄になって真っ赤に焼けてしまったような感覚である。その瞬間、右隣りの本棚に烈しい爆発音がした・・・私はフロイトに言った。『これこそ正に媒体による外在化現象の一例です』『おお』と彼は叫んだが、『それは、たわごとにすぎん。』と言った。『いや、ちがう。』と私は答え、『先生、あなたは間違ってらっしゃる。そして私の言ったことが正しいか、どうかは、すぐにもう一度、あんな大きな音がすることでお分かりになります』と、私がそう言うが早いか、全く同じ爆発音が本棚の中で起こったのである。」
1913年にユングは、フロイトより訣別状を受け取りました。それから第一次世界大戦勃発、その後もナチスの勢力拡大や世界経済恐慌が襲う不安定な情勢の中、フロイトとユングはそれぞれに活躍します。ヒットラーがドイツの政権を握り、ナチスの迫害が激しくなってきた頃、ユダヤ人であるフロイトはロンドンに亡命、病死しました。ユングは、フロイトへの追悼文を書きました。
1945年、ユングはジュネーブ大学より名誉博士号を贈られ、1948年にはチューリッヒにユング研究所が創設されました。そして、ユングは1960年にキュスナハトにて世を去りました。ユングの生きた時代は、霊的なものをなかなか受け入れ難い時代にも関わらず、彼の論理は絶大な支持を浴び、フロイトにまさり、それは今に到っています。
ユングのところへ患者が来院すると、患者はユングに問題の対処法を訊ねます。しかしユングは、「全然分からない。」と答えます。患者はびっくりして、「あなたなら、ご存知だろうと思っていたのに。」と言います。ユングは、「私は、あなたの問題の解決法を知りません。しかし、夢があります。夢は、不偏不党の事実であり、それが情報を与えてくれるかもしれません。夢が何を言っているかを見ることにしましょう。」と言います。そして、患者が見た夢の分析を行っていきます。
夢には幾種類かあって、願望の夢や解放の夢などもあり、また霊夢と呼ばれる夢もあります。ユングは、患者の夢を読み解き、患者の心の中に潜む病理を引き出し、あるいは患者に告げられているメッセージを明らかなものとし、患者を治癒へと向かわせます。
しかし、夢による霊的な解釈は、この地上においてユングがやり始めたものではなく、太古から広く存在するものでした。古代ローマでは、夢は神からのメッセージだと信じられており、元老院では意味があると思われる夢の解釈に頼って政治を行っていました。またギリシャでは、しばしばアドバイザーとして、夢を読み解く人が指名されました。アフリカでは、治療師やシャーマンが病気を診断し治すために、そのヒントを夢に求めました。中国とメキシコでは、夢は毎晩魂が旅をするまったく別の次元なのだと考えていました。そこでは祖先たちが、慰めと知恵を分かち合おうと待っていてくれるのです。エジプトでは、夢は神聖なものと思われ、しかるべき司祭だけが解釈することを許されていました。いつの間にか、忘れ去られたような夢の解釈を、ユングという精神医学博士が用いることにより、再び近代に夢の意味を提示しました。
チューリッヒ湖の畔には、ユングが建てた塔のある家があります。そこには、ユングが彫った見事な絵柄の四角い石が、今も置かれています。ユングがその石を前にして立つと、いろんなものが見えてきて、それを彫ったそうですが、その石彫りも、夢の霊的解釈の復権も、彼の霊媒としての役割りだったのではないでしょうか。
瀬野彩子
参考文献
『精神分析入門』 フロイト(新潮社)
『夢判断』 フロイト(新潮社)
『自我論・不安本能論』 フロイト(人文書院)
『夢分析』 C・G・ユング(人文書院)
『自我と無意識』 C・G・ユング (思索社)
『無意識の心理』 C・G・ユング(人文書院)
『ユングの人間論』 C・G・ユング (思索社)
『ユング心理学概説』 C・A・マイヤー(創元社)
『夢の治癒力』 C・A・マイヤー(筑摩書房)
『夢と人間社会』 カイヨワ/グリューネバウム(法政大学出版局)
『ユンク そのイメージとことば』アニエラ・ヤッフェ(誠信書房)
『ユング自伝』ヤッフェ編(みすず書房)
『ユング』A・ストー(岩波書店)
『眠れぬ夜に読む本』遠藤周作(光文社)
『スピリチュアル・ドリーム』シルビア・ブラウン(PHP研究所)
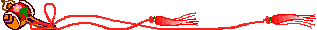
『 新樹の通信』について
『新樹の通信』とは、新樹(しんじゅ)という名前の青年の死後の通信を本にしたものです。
新樹は、明治37年に横須賀に生まれ、昭和4年に大連の満鉄病院で病死しました。そして約百日後、新樹は母、多慶子を媒体として、霊界通信を始めます。それは、父が心霊を研究している浅野和三郎であり、その手助けをしたいという新樹の強い思いがあった故に成し得ました。
新樹の霊界通信は、簡単な言葉のやり取りからはじまります。
父「おまえは、いま何かキモノを着ているか?」
新樹「着ています」
父「飲食はやるか?」
新樹「何も食べません」
父「睡眠は?」
新樹「睡眠もいたしません」
父「月日の観念はあるか?」
新樹「ありません。ちっとも」
父「おまえにも、きっと守護霊がついているはずだが・・・・つまり、おまえを指導してくださる後見人みたいな人が・・・」
新樹「ついております・・・。5人ついております」
以上のような通信から、次第に発展していきます。そして、通信している時の新樹の状態についても訊ねています。
新樹「(通信している最中は)ちょっと、何かその、ふるえるように感じます。細かい波のようなものが、プルプルプルプルと伝わって来て、それが僕の方に感じるのです」
父「私の述べる言葉が、おまえに聞こえるのとは違うのか?」
新樹「言葉が聞こえるのとは違います・・・感じるのです・・・。もっともお父さんの方で、はっきり言葉に出してくださった方が、よくこちらに感じます。僕はまだ慣れてないから・・・」
父「私に限らず、誰かが心に思えば、それがお前の方に感じるのか?」
新樹「感じます・・・いつも波みたいに響いて来ます。それは眼に見えるとか、耳に聞こえるとかいったような、人間の五感の働きとは違って、何もかも皆一緒に伝わって来るのです。現にお母さんは、しょっちゅう僕のことを想い出してくださるので、お母さんの姿も、心持ちも、一切が僕に感じてしょうがない・・・」
父「現在、おまえは以前の通り、自身の体があるように感じるか?」
新樹「自分というものがあるようには感じますが、しかし地上にいた時のように、手だの、足だのが、あるようには感じません・・・。といって、ただ空なのではない、何かがあるように感じます。そして造ろうと思えば、いつでも自分の姿を造れます・・・」
また、この『新樹の通信』では、墓についても言及しています。
「墓というものは、あれは人間界のみのもので、つまり遺骸を埋葬するシルシの場所であり
ます。こちらの世界に墓というものは全然ない。また、あるべき筋の物でもないと思いま
す。・・・いかに立派な墓を築いてくれても、こちらに必要がなければ、一向につまらないも
のです。・・・墓はただ華美を好む現世の人達を歓ばせるだけのものであります。といっても、もちろん墓を築くのが悪いというのではありません。遺族や友人が、墓に詣っても、名を呼んでくだされば、それはこちらにも感じますから、死んだ人の目標として、質素な墓を築くことは甚だ結構なことであります。ただ、あまりに華美なことをして貰いたくないと言うまで・・・」
新樹は、霊界で仕事をはじめますが、子ども達が通う霊界の学校についても語っています。
新樹「・・・学校のような場所へ連れて行って、見学させてくれました。一学級の生徒は、20人くらいで、やはりここでも男女合併教室としていました・・・」
父「生徒の服装は?」
新樹「皆まちまちで、一定していません。帽子などもかぶっていません」
父「書物だの、黒板だものあるか?」
新樹「皆、ひと通り揃っています。子どもが質問すれば、教師はそれに応じて、話をするらしく見えます」
父「教師は、どんな人物だったか?」
新樹「30歳前後の若い男でした。・・・この人は、生前に子どもを持たなかったそうです。・・・」
赤ちゃんや幼い子どもが亡くなると、生前に子どもを持たなかった人が子守役になるという話はよく聞きますが、霊界の学校の教師も、生前に子どもを持たなかった人が行っているようです。
浅野和三郎は、『新樹の通信』を出版したことについて、こう記しています。
「亡児の通信の内容は、必ずしも発表に適しません。私的関係以外には、むしろつまらないものが多く、また感情から言っても、これを公表するに忍びないのが多いのであります。私がこの数年間、ほとんど亡児の通信に手を触れなかった所以であります。
が、翻って考えうれば、日本の心霊学界の現状はあまりにも貧しく、あまりにもさびしく、・・・首肯し得るほどの純真な霊界通信はほとんど何所からも現れていないのであります。・・・成るべく悩める人の心の糧になりそうな個所を拾い出すつもりでありますが、・・・未完成な一青年からの私的通信であります・・・」
朴訥とした『新樹の通信』だからこそ、信憑性も増し、後世にも伝えられる書となったのだと思います。
参考文献
『新樹の通信』浅野和三郎(潮文社)
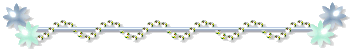
『シルバー・バーチの霊訓(四)より
1920年代後半から50年余りにかけて、古代霊シルバー・バーチがイギリスに降臨、人類に訓戒を授けました。それは世界で刊行され、日本でも『シルバー・バーチの霊訓』全十二巻として訳され、今も多くの人に愛されています。
まるで美しい調べが響くようなシルバー・バーチの言葉の数々には、尖鋭な訓戒が並びます。
「死んだ人達は、あなたのもとから去ってしまうのではありません。死という名のドアを通り抜けて、新しい生活へ入っていくだけです。その人達にとって、死は大きな解放です。決して苦しいものではありません。彼等にとって唯一の辛さは、地上に残した人々が自分のことで嘆き悲しんでいることです」
しかし、私達は愛する人を亡くすと、どうしても酷く嘆いてしまいます。死以前のように愛する人と触れ合い、労わり合い、面倒をみることも出来ないのですから。愛する人を亡くしてしまったという自分の人生を憂いさえします。
「自分は、神の一部のなのだ。不滅なのだ。永遠の存在なのだ。無限の可能性を宿しているのだ。その自分が限りある物質界のことで挫けるものか、と。そう言えるようになれば、決して挫けることはありません」
とシルバー・バーチは言いますが、果たしてどうしたらそのような思いに至るのでしょうか。
まずは、知識をもつことだとシルバー・バーチは言います。
「知識というものは、自分より先に歩んだ人の経験の蓄積ですから、勉強してそれを自分のものにするよう努力した方がいいでしょう。私は、そう思います」
そして、シルバー・バーチが当初より唱え続けている人助けについても言及します。
「自分を愛するごとく、隣人を愛することです。人のために役立つことをすることです。自分を高めることです。何でもよろしい。内部に宿る神性を発揮させることをすることです。・・・いちばん偉大なことは、他人のために己を忘れることです。自分の能力を発揮させること自体は結構なことです。が開発した能力を、他人のために活用することの方が、もっと大切です」
また、大空の会のような会合を持つことの大切さを語ります。
「心の通い合える人々が、同じ目的をもって一つのグループをつくります。・・・目的、動機がいちばん大切です。面白半分にやってはいけません。・・・忍耐強く、ねばり強く、コンスタントに会合を重ねていくことです。同じ一念に燃えたスプリットと感応し、必要な霊能を発揮すべく援助してくれるでしょう。
言っておきますが、私どもは何かと人目を引くことばかりしたがる見栄っ張りの連中に用はありません。使われずに居睡りしている貴重な能力を引き出し、同胞のため、人類全体のため有効に使うことを目的とした人の集まりには、大いに援助します」
このシルバー・バーチの言葉の中の、一念に燃えたスピリットとは、シルバー・バーチ自身のことでもあり、同時に私達にとっては、天国に行った子ども達のことではないでしょうか。シルバー・バーチは、こうも教えてくれます。
「あなたが愛し、あなたを愛してくれた人々は、決してあなたを見捨てることはありません。いわば愛情の届く距離を半径とした円の範囲内で、常にあなたを見守っています。時には近くもなり、時には遠くもなりましょう。が決して去ってしまうということはありません。
その人達の念が、あなた方を動かしています。必要な時は強く作用することもありますが、反対にあなた方が恐怖や悩み、心配の念で壁をつくってしまい、外部から近付けなくしていることがあります。悲しみに涙を流せば、その涙があなたの愛しい霊までも遠くへ流してしまいます。
穏やかな心、やすらかな気持ち、希望と信念と自信に満ちた明るい雰囲気に包まれている時は、そこに愛しい霊や、多くの素晴らしい霊達が寄ってまいります」
知識を得、人を愛し、そして助け、同じ目的をもつ者達の向上を目指した会合を続けることによって、おのずとネガティブなものより遠ざかり、前進することができると、シルバー・バーチは教示します。
大空の会は、吐露するだけに終わらず、学びを取り入れることにより知識を得、お互いに助け合うことを信条とし、毎月一回の会合を重ねています。半世紀前より大空の会の存在を予言しているようにさえ思うシルバー・バーチの言葉です。きっと大空の会の存続の謎は、シルバー・バーチの言うように霊界からの大いなる援助を受けているからなのでしょう。
さらにシルバー・バーチは、私達を奮い立たせるような言葉を与えてくれます。
「決して弱気になってはいけません。堂々と胸を張り、宇宙を創造した力、夜空にきらめく星を支えている力、花に香を添え、太陽を昇らせ、そして沈ませる力、虹にあの美しい色彩を施し、小鳥にあの可憐なさえずりを与えた力、全生命に存在価値を与え、人間に神性を賦与した力、その力がいつもあなた方を支え、守り、そして導いていることを忘れてはなりません」
この世の中を生きるのは、楽しいことも嬉しいこともたくさんありますが、悲嘆、畏怖、憂慮などに苦しめられる時、『シルバー・バーチの霊訓』を開けば、どこかにその答が出ています。そして読み続けていけば、シルバー・バーチが灯明をもって導くように、その行き先を提示してくれます。
これからも『シルバー・バーチの霊訓』は、人々の永遠の珠玉の書として在り続けるのだろうと思います。
瀬野彩子
参考文献
『シルバー・バーチの霊訓(四)』潮文社 訳:近藤千雄
『古代霊は語る』潮文社 訳:近藤千雄
 大空の会より
大空の会より 


 ナイチンゲール「愛の灯火」
ナイチンゲール「愛の灯火」

 ユングの世界
ユングの世界